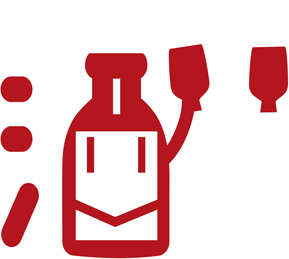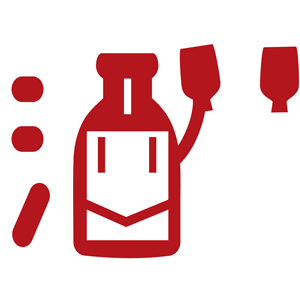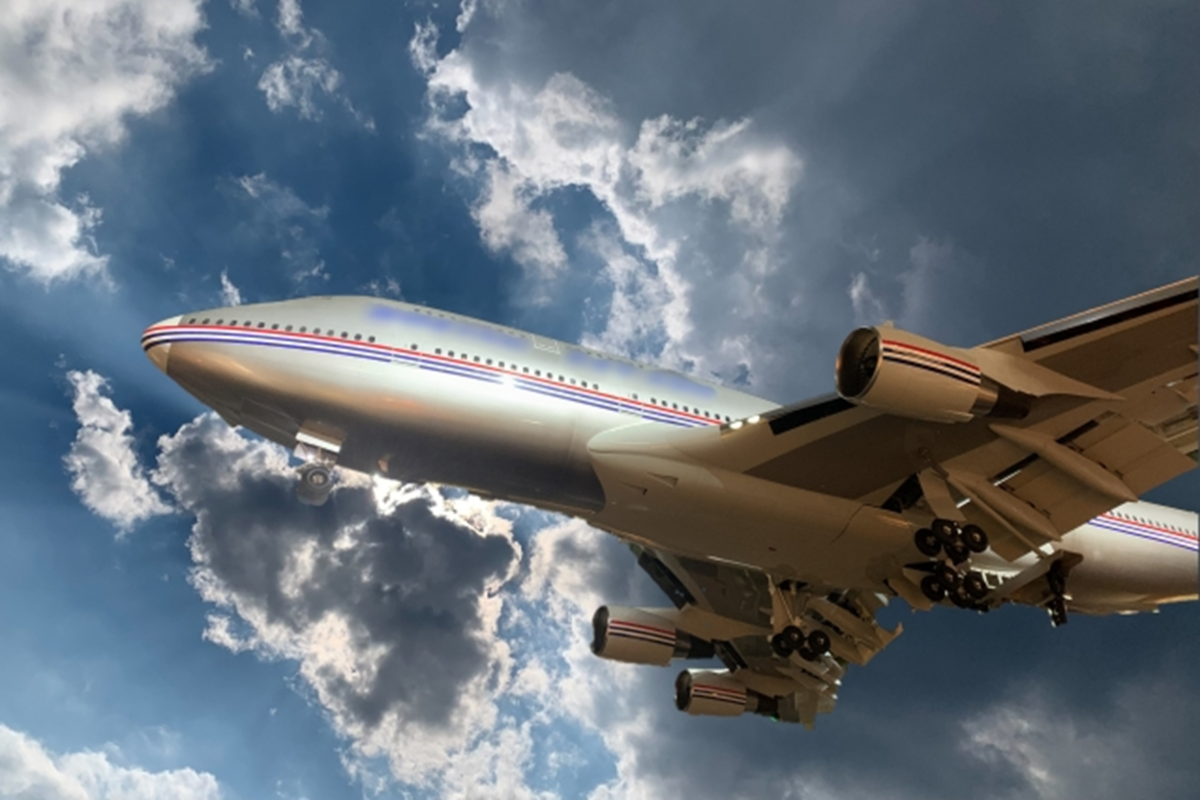世界市場で「SAKE」はどう戦うべきか? 輸出戦略のリアルを「獺祭」桜井社長らトップランナーが徹底討論
SAKETOMOをご覧のみなさん、こんにちは。日本酒ライターの関 友美です。
私の仕事は、ただ日本酒を味わうだけでなく、その一杯に隠された「酒と地域の物語」を丁寧にすくいあげ、皆さんに届けること。実際に6年間、酒蔵で酒づくりに携わった経験があるからこそ、その物語の尊さを肌で感じています。
今回は、まさにそんな物語が凝縮された、年に一度の特別なイベント『SAKE LEADERS SUMMIT(サケリーダーズサミット)』の現場から、一歩踏み込んだレポートをお届けします。
「日本酒って、海外で人気なんでしょ?」
最近、そんな声をよく耳にします。しかし、その華やかなイメージの裏側で、日本の蔵元たちがどんな現実に直面し、どんな未来を描いているのか、その「生の声」に触れる機会は意外と少ないのではないでしょうか。
この記事を読み終える頃には、あなたが次に手にする一杯の日本酒が、少し違って見えるかもしれません。そのラベルの向こう側にある、壮大な挑戦の物語を、ぜひ一緒にのぞいてみましょう。
世界を見据えるトップランナーが集結! 注目のトークセッション
2025年7月、業界関係者が集う「国際発酵・醸造食品産業展」の中で、ある画期的なイベントが初めて開催されました。それが「サケリーダーズサミット」です。私は全11セミナー中8つを聴講しました。日本酒の未来を本音で語り合うこのサミットの中でも、私が特に注目したのは、「世界のアルコール市場をつかむために —— 制度と実務を踏まえた日本酒輸出の実態と次の戦略」と題されたトークセッションでした。
まさに、海外で日本酒を広めるためのリアルな戦略会議。登壇したのは、業界の最前線を走る、そうそうたる顔ぶれでした。
【登壇者】
・ 桜井 一宏さん(株式会社獺祭 代表取締役社長)
・ 保井 久理子さん((独)日本貿易振興機構 農林水産食品部 次長)
・ 戸塚 康文さん(マッキンゼー・アンド・カンパニー パートナー)
・ 坂根 正敏さん(国税庁日本産酒類輸出促進コンソーシアム 専門家)
・ 宗京 裕美子さん(Sake Suki CEO)
【ナビゲーター】
・ カワナ アキさん(camo株式会社 代表取締役)
蔵元、国の機関、コンサルタント、そして輸出の実務家。それぞれのプロフェッショナルが語る言葉から見えてきたのは、私たちが普段知ることのない、世界で戦う日本酒のリアルな姿でした。
「獺祭でさえ、まだ知られていない」— 海外での日本酒のリアルな現在地
トークセッションは、ナビゲーターのカワナさんからの「輸出の現状はどうですか?」という問いかけで始まりました。最初にマイクを握った獺祭の桜井社長から飛び出したのは、いきなり私たちのイメージを覆す、驚くべき言葉でした。
桜井 一宏さん(以下、桜井さん) 「海外だと、実際まだまだ知らない人が多いなっていうのが、私たちの実感ですね。まあ、お酒(SAKEというカテゴリー)はなんとか知ってる。でも、個々の銘柄はよく分からない、という状態が多いなと思っております」
世界を席巻しているように見える獺祭でさえ、一般の消費者レベルではまだ個別の銘柄までは認知されていない。この事実は、セッションの冒頭で提示された、最も重要な「現在地」でした。
「まだ戦える場所はある」—香港、そしてインドへ
そもそも、なぜこれほどまでに海外市場が重要なのでしょうか。背景には、国内市場の厳しい現実があります。人口動態の変化により、日本の日常的飲酒人口は今後40年で半減するとの見通しもあり、海外に活路を見出すのは必然なのです。
では、その海外市場はすでに飽和状態なのでしょうか? 長年、海外での日本酒ビジネスの現場を見てきた坂根専門家は、その見方を否定します。
坂根 正敏さん 「香港市場を『レッドオーシャン(競争の激しい市場)だ』と見る方もいますが、総アルコール売上に占める日本酒の割合はまだ1.5%ほど。ブルーオーシャンではないかもしれませんが、開拓の余地は十分あります」
さらに、坂根さんは未来の巨大市場としてインドを挙げ、「人口は世界一。宗教上の制約はあっても、飲酒できる州の方がずっと多い。ブルーオーシャンを目指していくべき」と力強く提言しました。
つまり、海外での日本酒は「一部の熱心なファンには深く刺さっているけれど、市場全体で見ればまだまだ小さな存在」。だからこそ、未来には大きな可能性があるのです。
桜井社長が語ったこの言葉も、その現状を的確に表しています。
桜井さん 「アメリカ市場の全アルコールの中で、日本酒はまだ0.2%のシェアしかありません。これは、日本におけるアメ車(0.4%)のシェアよりも少ない。それだけ、これから伸びる可能性がある、本当に大きな市場なんです」
この巨大な未開拓市場に、日本の蔵元たちはどうやって漕ぎ出そうとしているのでしょうか。そこには、私たちが想像する以上に、いくつもの大きな壁が立ちはだかっていました。
温度、契約、ニセモノ…? 世界へ届けるためのリアルな壁
素晴らしい日本酒を造っても、それが最高の状態で海外の飲み手のグラスに注がれなければ意味がありません。
課題①:品質を守る「コールドチェーン」の壁
北米で高品質な日本酒の輸入を手がける宗京さんは、現地の小売店の状況をこう話します。
宗京 裕美さん(以下、宗京さん) 「アメリカのワインストアでは、まだまだ冷蔵庫が完備されていません。ワイン文化が根付いているため、白ワインの温度帯(10℃〜15℃)が基本。日本酒のために冷蔵(5℃以下)の設備を置いてください、と説明して回るレベルの段階なんです」
最後の売り場での温度管理まで徹底するには、地道な働きかけが不可欠なのです。
課題②:「信頼」をどう築くか、契約と関係性の壁
さらに深刻なのが、契約や商標の問題です。坂根専門家は「以前アメリカで扱っていた22蔵のうち、ディストリビューターやインポーターと正式な契約書を交わしていたのは2蔵だけでした」と、あまりにも無防備な実態を明かし、口約束の危険性を指摘します。
さらに、たとえ契約書を交わしている場合でも、その多くは相手方が用意した書面にサインするだけ、というケースがほとんどです。この日の議論では、自社のブランドと『日本酒』という文化を守るためには、むしろ酒蔵自身が主体的に契約書を準備し、相手に提示していくくらいの強い姿勢が不可欠だと強調されました。
こうした状況に対し、国の支援策との向き合い方について、JETROの保井さんが非常に重要な視点を示しました。JETROなどが行うバイヤー招聘事業は有効な一方、桜井社長が指摘するように「相性が合わない相手と付き合ってしまうリスク」も伴います。
安易に支援に頼るのではなく、あくまで蔵元自身が主体的に判断すべきだと、保井さんは語ります。
保井 久理子さん 「国の事業に依存すると、『その中から取引相手を選ばなければならない』という発想になってしまう。そうではなく、『利用してやろう』くらいの気持ちで、自分たちでしっかり事前準備をして主体的に活用してほしいのです。実際に田んぼや製造現場を見てもらうことで、言葉だけでは伝わらない情熱が伝わり、それが強固なパートナーシップに繋がります。海外のバイヤーにファンになってもらうことが何より重要です」
常に契約書を重視する獺祭・桜井社長でさえ「うちは五大陸で裁判を起こすのが目標」と冗談めかすほど、海外では思わぬトラブルが絶えません。特に、この日明かされた「獺祭」とウイスキー「山崎」を合わせた『獺崎』のような巧妙な模倣品の存在は、その深刻さを物語っています。
こうしたリアルな壁を乗り越えるには、書面での契約という土台と、顔の見える関係づくりという信頼の両輪が不可欠なのです。
プレミアムか、マスか? 世界の心をつかむための次なる戦略
では、こうした課題を乗り越え、日本酒を世界でどう位置づけていくべきか。ここで、非常に興味深い戦略論が交わされました。
コンサルティングファーム、マッキンゼーの戸塚さんは、まず最高品質の体験を提供し、トップダウンで価値を伝えていく戦略を提案します。
『ファン』の育て方はどう変わる?ソーシャルメディアが拓く新時代
では、その「ファン」をどうやって育てるのか。宗京さんは、現代ならではのアプローチを語ります。
宗京さん 「YouTubeやインスタグラムを通じて、日本で今何が人気で美味しいのかという情報が、米国の消費者にしっかり届いています。20代、30代前半のアンテナが高い、若い飲み手が育っているのをすごく感じますね」
ファンになる最初のきっかけは「レストランでの美味しい体験」から探求心が始まることが多いそう。そして、ソムリエがワインと同様に日本酒のストーリーを語ることが、その価値を深く伝えているのです。
一方で、獺祭の桜井社長は、プレミアム市場と、より広い市場の両方にアプローチする「両輪戦略」の重要性を語ります。
桜井さん 「レストランでの特別な体験と、リカーショップやスーパーでの日常的な出会い。この二つが影響し合い、お客様との接点を増やしていくことが、まだ日本酒が広く知られていない市場では非常に大切だと考えています」
【ライターズ・レコメンド】明日からの一杯がもっと楽しくなる、3つの視点
さて、ここまで世界で戦う日本酒のリアルな姿を見てきました。こうした背景を知ると、私たちが普段、何気なく手に取る一本の日本酒にも、壮大な物語が隠されていることに気づかされます。
そこで最後に、このトークセッションを踏まえ、皆さんの日本酒選びがもっと楽しくなる、具体的なヒントを3つの視点でレコメンドさせてください。
1. 「世界が認めた味」の目印、海外コンクールのメダルを探してみる
「たくさん種類があって、どれが美味しいのか分からない…」という方は、まずボトルの首やラベルに貼られたメダルシールを探してみてはいかがでしょうか。
近年、海外では日本酒の品質を評価する様々なコンクールが開催されています。中でも特に有名で、ボトルに貼られたメダルシールを見つけやすいのが、ロンドンで毎年開催される世界最大級の品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ(IWC)」です。世界中の専門家がブラインドで選んだお墨付きは、味わいの確かさを示す、信頼できる目印になります。
フランスの「Kura Master」をはじめ、他にも権威あるコンクールはあります。まずはこの「世界が認めた目印」を頼りに、自分好みの一本を見つける冒険に出てみるのがおすすめです。
2. ちょっと特別な日には「空飛ぶお酒」を選んでみる
大切な方への贈り物や、自分へのご褒美には、航空会社の国際線ファーストクラスやビジネスクラスで採用されているお酒を選ぶ、というのも素敵な方法です。JALやANAなどの公式サイトでは、機内で提供されている日本酒のリストが公開されており、世界のお客様をもてなすために厳選された一本を知ることができます。
3. 地元の酒を「世界目線」で味わい、応援する
海外で評価されるのは、有名な大手の蔵だけではありません。行きつけの酒屋さんで地元の酒を手に取ったとき、「もしこのお酒が、ニューヨークのレストランのリストに載ったら?」と想像してみてください。そのポテンシャルを「世界目線」で味わい、SNSなどで発信することが、私たちにできる最高のエールなのかもしれません。
桜井社長は、セッションの最後に力強くこう締めくくりました。
桜井さん 「デフレだからもう無理だ、なんてことは絶対にありません。世界はレッドオーシャンではなく、まだまだ可能性に満ちたブルーオーシャンです。日本の酒蔵が、そして日本酒という文化が、この世界の大きな舞台へ挑戦していくこと。それを、ぜひ皆でやっていきたいのです」
世界という広大な海は、まだ青く広がっています。
私たちが応援の気持ちを込めて、今日、一杯の日本酒を美味しくいただくこと。それもまた、大きな船を未来へと進める、確かな追い風になるのかもしれません。
関連記事