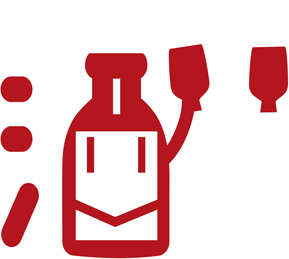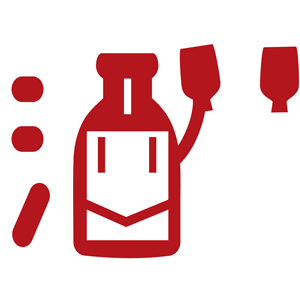伊達政宗は酒癖が悪かった? 「にっぽん城まつり」名古屋国税局ステージで日本酒の伝統を再発見
-

城と日本酒の祭典「にっぽん城まつり 2025」
毎年恒例となっている城と日本酒の祭典「にっぽん城まつり2025」が2025年3月1日(土)2日(日)の2日間、名古屋の吹上ホール(名古屋市千種区)で開催。全国各地から城に関する専門家や武将隊が集い、「にっぽん酒まつり」コーナーでは東海三県の美味しい日本酒やグルメも楽しめるイベントということもあり、2日間ともに会場は大いに賑わっていました。
-

各地から武将も集結
同イベントでは、日本酒を始めとした伝統的酒造りがユネスコ無形文化遺産に登録されたことを記念し、名古屋国税局がトークイベント「城と武将と酒の良い話」を実施。歴史学者の平山優先生、元NMB48メンバーで現在は「ゆい酒店」オーナーを務める高野祐衣さん、関谷醸造専務取締役の遠山久男さんらが登壇し楽しいトークを繰り広げました。
-

左から平山優先生、高野祐衣さん、遠山久男さん
今回は、お城ファンも日本酒ファンも楽しんだ「にっぽん城まつり」の模様を、名古屋国税局ステージでのトークショーの内容を中心にお伝えします。
城と武将と日本酒の意外な関係 酒癖が悪かった有名武将とは
ステージの冒頭では、名古屋国税局長の湯下敦史氏が登壇。挨拶の中で、「歴史や文化の面から見ても、日本酒は城とともに日本らしさを非常に象徴しているものである」とし、「日本が世界に誇る伝統的酒造りに興味を持っていただき、若い世代や外国の方にも日本酒の良さをどんどん広げていきたい」と、ユネスコ無形文化遺産への登録を機に日本酒や酒造りに注目が高まることに期待を寄せました。
-

名古屋国税局長 湯下敦史氏の冒頭挨拶
続いて会場全体で乾杯。乾杯酒として関谷醸造の「蓬莱泉 純米吟醸 BLACK」が用意され、登壇者たちが早速舌鼓を打っていました。
-

乾杯の日本酒となった「蓬莱泉 純米吟醸 BLACK(関谷醸造)」
酒造りは重労働! 麹造りは「ほぼサウナ」!?
乾杯が終わると、日本酒を片手にトークがスタート。まずは遠山専務から日本酒造りの工程についてVTRを交えながらの解説が行われました。
洗米・浸漬から上槽までいくつもの工程を経て行われる日本酒造り。出来上がるまでには約1ヶ月という長い時間がかかります。遠山専務によると、発酵が進んでお酒ができてくるとプチパチと弾ける心地いい音が聞こえてくるとのこと。搾られたお酒がチョロチョロと流れてくる様子も、まるで雫のような美しさと言います。
一方で、日本酒造りでは麹造りや櫂入れなどの様々な工程で重労働が伴います。毎年酒蔵に出向いて麹造りに参加しているという高野さんは「ほぼサウナみたいな感じで、ダイエットだと思って入っています」と、その大変さを語っていました。
伊達政宗は酒乱だった!? 切っても切れない城と武将とお酒の関係
「城と武将とお酒」をテーマとした今回のトークイベント。テーマにちなんで、「国内で唯一城内に酒造屋敷がある城はどこ?その城を作った武将は誰?」というクイズも出題されました。皆さんは答えが分かりますか?
正解は「伊達政宗が築いた仙台城」。仙台城の城内大手口を入った少し奥の場所に酒造屋敷があったとされ、近年の発掘調査でも跡地が発見されたそうです。
ちなみに平山先生にとって伊達政宗は「絶対に一緒にお酒を飲みたくない武将」とのこと。というのも、伊達政宗は筆まめで有名なのですが、残された手紙の中には「二日酔いで会議を欠席する言い訳」や「お酒の勢いで殴ってしまった家臣への詫び状」なども多数残っており、相当酒癖が悪かったようです。
-

平山先生から伊達政宗の“酒癖”エピソードが披露
一方、思わぬ形で日本酒の“被害者”となってしまったのが今川義元。桶狭間の戦いの際、戦いの途中にも関わらず戦勝祝いで酒盛りをしていたところを織田信長に不意を突かれて負けてしまったという逸話がよく知られています。しかし、平山先生によるとこれは「フィクション」とのこと。この逸話は天下人や英雄に討たれた人間は無能だと印象付けるために、後世になって作られた話の可能性が高いそうです。
戦国時代の日本酒はどんな味?
続いての話題は戦国時代のお酒について。戦国時代は精米技術も未発達で現在のような道具も無いため、玄米に近いような米で作られたお酒だったと考えられています。また、搾りの技術も発展しておらず、現代のような清酒ではなく、どぶろくに近いものか、少し濾過した程度の白く濁ったものが飲まれていたそうです。
さらに当時のお酒は現在の清酒よりもアルコール度数が低かったとのこと。例えば黒田節の中には戦国武将の一人である母里太兵衛が大酒を飲んで槍を授かったという逸話がありますが、平山先生からはこれも現代よりもアルコールが低かったためたくさん飲むことができたのではないかとの説が紹介されました。
ここでステージには昔の製法で造られた日本酒である「Tsuchida 菩提もと×生もと(群馬県・土田酒造)」が登場。登壇者たちで一緒に試飲が行われました。
少し黄色みがかった日本酒は、アルコール度数がやや低め。高野さんからは「しっかりと乳酸菌由来の酸味が感じられる、好みのタイプのお酒です」と、遠山専務からは「食を何か合わせたい」とそれぞれ好印象のコメントが上がりました。平山先生は、あっという間に杯を空っぽにすることで美味しさを表現。言葉が無くてもその美味しさはしっかりと伝わってきました。
日本酒を造る鍵となる「麹」を試食
最後の話題は、日本酒造りの鍵を握る存在である「麹」について。日本酒造りで欠かせないコウジカビを実際に「舌」で体験しようと、ステージ上に麹付けした酒米が用意されました。
試食した高野さんは、その味わいを「ちょっと水分の少ない栗」と表現。甘い味わいや香りが栗のようで、プチプチとした食感も楽しめるようでした。
ステージ終了後には国税局ブースで来場者も麹米の試食を体験することができました。筆者も貴重な麹米を分けていただきました。
-

名古屋国税局ブース
麹によりデンプンの分解が進んだ酒米は、ほんのりと穏やかな甘さ。適度な硬さの中にホロッとした食感が心地良く、炊いた米とは異なるスッキリとした甘さが感じられました。
会場で麹米を試食した人に話を聞いてみたところ、その甘さに驚いていた様子。初めて麹米を試食したという方ばかりでしたが、「スプーンですくっていっぱい食べてみたい」「プチプチの食感もあるので、お菓子のデザートに使っても面白そう」などの話が聞かれました。
「にっぽん酒まつり」ゾーンも大盛り上がり!
今回の「にっぽん城まつり」では、「にっぽん酒まつり」ゾーンとして東海三県から11の酒蔵が出店。各蔵自慢の日本酒を飲み比べながら楽しめることもあり、多くのお客さんで賑わっていました。
出店酒蔵の1つである若葉(岐阜県瑞浪市)のブースでは、岐阜県で42年ぶりに誕生した新品種の酒造好適米「酔むすび」を使った日本酒「若葉 酔むすび 純米大吟醸生原酒 ファーストエディション」が登場。「酔むすび」の個性が反映された新しい日本酒は、甘味がありながらもスッキリと飲みやすい、味わいのある仕上がりとなっていました。
「酔むすび」を使った日本酒は令和6酒造年度より東濃地域の9つの酒蔵で醸造が行われていること。「若葉 酔むすび 純米大吟醸生原酒 ファーストエディション」は、4月6日(日)に開催の蔵開きイベント「蔵元若葉 酒蔵特別公開」でも試飲可能とのことです。
日本酒の魅力を再発見できる貴重な機会に
「にっぽん城まつり」で行われた名古屋国税局ステージでは、城と武将と日本酒という意外な組み合わせから歴史や文化の奥深さを感じることができました。ユネスコ無形文化遺産にも登録され世界的にもますます注目を集める日本酒。その伝統と革新に触れることで、改めてその魅力に気づく貴重な機会となりました。
-

国税局ブースでは伝統的酒造りのユネスコ無形文化遺産登録を記念したノベルティーも配布されました
「にっぽん城まつり2025」概要
タイトル にっぽん城まつり2025
開催日時 2025年3月1日(土)2日(日)
会場 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホール
ホームページ https://shiromatsuri.com/
関連記事